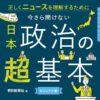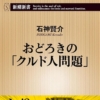ストーカー被害がメディアでもよく取り上げられますが、ストーカーになる人の心理とはどういうものなのでしょうか?また、ストーカーから被害を受けないようにするにはどのようなことに注意すべきなのでしょうか?

ストーカー加害者の心理は、揺るぎない被害者意識や激しい思い込み、愛憎入り交じった執拗さなどを特徴とし、失恋後のグリーフワークが停滞することで相手への執着を断ち切れないケースが多いです。加えて、自尊心の回復や関係再構築を動機とする「拒絶型」や、妄想的愛情から執拗に迫る「関係妄想型」などのタイプに分かれます。一方、被害を防ぐためには初期のつきまとい行為や執着行動を軽視せず、警察や専門相談機関に早期相談するとともに、携帯ブザーの携帯や住居の二重鍵設置など具体的な防犯対策を講じることが有効です。
- ストーカー加害者の心理的特徴
1.1 根本的心理構造
ストーカー加害者は、対象に対する“揺るぎなき被害者感情”を抱き、相手から拒絶された事実を認められず強い怒りや悲哀を反芻し続ける傾向があります。
このため、グリーフワーク(悲嘆の受容プロセス)の第1~3段階(失った事実を認められない、諦めきれず怒りを感じる、混乱・絶望する)に停滞し続け、関係修復の妄想や復讐心がエスカレートしやすいとされます。
1.2 主な動機・タイプ分類
オーストラリアのリスク評価手法「Stalking Risk Profile」によると、動機や関係性、精神病理性の有無から以下の5タイプに分類されます:
- 拒絶型:元配偶者や恋人からの拒絶をきっかけに関係修復や復讐を図る。
- 憎悪型:一方的な憎しみに基づき恐怖やダメージを与えようとする。
- 親しくなりたい型:知人・同僚への過剰な親密さを求める。
- 関係妄想型:実際には近しい関係がないにもかかわらず、執拗に愛情を押し付ける。
- 略奪型:既に関係のある第三者から対象を奪おうとする。
さらに、あさがお不動産の調査では「家庭内支配」「欲望達成」「拒絶過敏」「有名人ファン」「政治的目的」「復讐目的」など多様な動機が報告されています。
- 加害者に見られる行動パターンと病理
2.1 愛憎入り混じった執拗さ
愛情と憎悪が交錯し、相手を身近に感じることで自尊心が補強されるため、つきまとい・待ち伏せ・電話・SNS等による嫌がらせ行為を繰り返します。
近年ではGPS悪用やネットストーカー(SNSでの監視・嫌がらせ)も増加し、被害の多様化・深刻化が懸念されています。
2.2 自己中心的な被害者意識
加害者は自分を「傷ついた被害者」と認識し、相手の拒絶や無視を過剰に解釈しがちです。
また、多くが自身の行為を「愛情表現」や「正当なリアクション」と自己正当化し、他者からの助言や治療的介入を拒否する傾向があります。
- 被害を受けないための注意点
3.1 初期兆候の認識と対応
- つきまといや待ち伏せなど初期のストーカー行為を軽視せず、発生直後に記録(日時・場所・行動内容)を残す。
- 不審電話やSNSメッセージはスクリーンショット等で保存し、電話会社・SNS運営者に相談する。
3.2 警察・専門機関への早期相談
- 最寄りの警察署に相談し、警告や禁止命令による法的措置を求める。
- DV相談窓口や市区町村の相談センター、女性相談ホットラインなどの専門機関を活用する。
3.3 日常生活での防犯対策
- 防犯ブザーや携帯電話の110番登録を常に携帯し、緊急時に助けを呼びやすくする。
- 住居のドア・窓に二重鍵やドアスコープを設置し、不審者の侵入リスクを低減する。
- 夜間の一人歩きは避け、人通りの多い明るいルートを選ぶようにする。
ストーカー被害の予防には、加害者心理の理解と初期段階での法的・物理的対応が不可欠です。早期に行動を記録し、警察や専門相談窓口へ連絡するとともに、日常的に防犯意識を高めることで被害リスクを大幅に軽減できます。