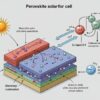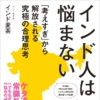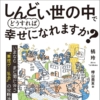日本の政治家は、増税を繰り返し日本経済の活性化をするどころか経済を停滞させているのですが、根本の原因として考えられるのは財務省の役人の考え方ではないかと思いますが、経済を発展させて増収による財政安定を考えられないのはなぜでしょう?

日本の政治家が繰り返し増税を行い、経済が停滞しているというご指摘、そしてその原因として財務省の考え方を挙げられている点について、様々な視点から分析してみましょう。増収による財政安定ではなく、増税による財政安定を志向するように見えるのはなぜか、その背景には複雑な要因が絡み合っています。
- 財務省の「財政健全化」至上主義
財務省は、国の財政を健全に保つことを最大の使命としています。これは、巨額の政府債務(国の借金)が年々膨らみ、将来世代に大きな負担を残すことへの強い危機感に基づいています。国際的にも日本の政府債務残高はGDP比で非常に高く、デフォルト(債務不履行)リスクを懸念する声もあります。
このため、財務省の基本的な考え方は「歳出(支出)を抑制し、歳入(収入)を増やす」というものです。特に歳入については、経済成長による自然増収を待つよりも、確実な増税によって手っ取り早く財政赤字を削減しようとする傾向が強く見られます。彼らにとって、「増税」は財政規律を保つための最も直接的で確実な手段と映るのかもしれません。
- 経済成長を主導する機能の欠如
財務省は、その名の通り「財政」を所管する省庁であり、経済成長戦略を立案・実行する役割は、経済産業省や内閣府などが担っています。財務省の主要な関心は、あくまで「いかに財源を確保し、予算を配分するか」という点にあります。
もちろん、経済成長が税収増につながることは財務省も認識していますが、彼らの組織文化や専門性は「財政規律の維持」に特化しており、積極的に経済成長を促すための政策(例えば、大胆な財政出動や規制緩和など)を主導することには慎重な姿勢を見せることが多いです。
- 硬直的な予算編成プロセスと歳出圧力
日本の予算編成プロセスは非常に複雑で、各省庁からの要求が積み上げられる形で行われます。少子高齢化が進む中で、社会保障費(医療、年金、介護など)は年々増加の一途をたどり、これが歳出の大きな部分を占めています。これらの経費は、国民の生活に直結するため削減が非常に困難です。
このように構造的に歳出圧力が高まる中で、新たな財源を確保しなければ、現在のサービス水準を維持できないという切迫感があります。経済が低成長である現状では、増収による財政改善が期待しにくく、どうしても「確実な増税」に頼らざるを得ないという側面もあるでしょう。
- 政治家の責任と国民の支持
政治家が増税路線を選択する背景には、財務省の影響力だけでなく、政治家自身の責任、そして有権者の意識も関係しています。
- 短期的な視点: 経済成長戦略は、効果が出るまでに時間がかかるものが多く、選挙を控えた政治家にとっては、短期的に効果が見えやすい政策(例えば、バラマキや減税による一時的な景気刺激策)に傾倒しやすい傾向があります。
- 国民への説明不足: 増税の必要性やその使途について、国民が納得できるような丁寧な説明が不足していると感じることもあります。その結果、増税への不満が高まり、消費が冷え込む悪循環を生むこともあります。
- 「痛み」の受容の難しさ: 財政健全化のためには、歳出削減という「痛み」も伴います。しかし、特定の分野への予算削減は、その分野の支持層からの反発を招くため、政治家は歳出削減に及び腰になりがちです。結果として、比較的国民に広く負担を求める増税が選択されやすくなります。
結論
財務省が増税路線を志向するように見えるのは、彼らの「財政健全化」という揺るぎない使命感と、そのための最も確実な手段としての「増税」への強いコミットメントがあるためと考えられます。経済成長による増収というアプローチは、時間がかかり不確実性が高いため、喫緊の財政課題を解決するには効率的ではない、と判断しているのかもしれません。
しかし、経済学的には、過度な増税が経済活動を抑制し、結果的に税収の伸びを鈍化させる(ラッファー曲線)という指摘もあります。経済成長と財政健全化のバランスをどう取るか、そして国民が納得できる形でそのバランスを示すことができるかどうかが、今後の日本の財政と経済の鍵となるでしょう。