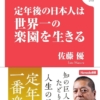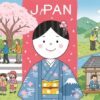家族が自宅で亡くなった時など、救急車を呼ぶことになりますが場合によっては救急車も対応してくれない場合もあります。遺族にとってはさらに辛いことにもなりかねません。これを避けるにはどのようにするのがよろしいのでしょうか?

自宅で家族が亡くなった場合、かかりつけ医がいないと「救急車を呼んでも対応してもらえず、結果的に警察対応になり遺族にとって精神的負担が大きくなる」ことが多く指摘されています。
鬼岩正和氏が『心に鬼を 魂に炎を』の中で触れているような、遺族がさらなる苦しみに追い込まれる事態を避けるため、以下の準備と対策が非常に有益です。
✅ 推奨される備えと対策
- かかりつけ医(在宅医)の確保と連携
- 訪問診療が可能な医師や在宅医療チームに事前に登録し、緊急時に連絡できる体制を整備しましょう。
- ベッドサイドや冷蔵庫など目に留まりやすい場所に、医師・訪問看護師の連絡先を保管しておくと安心です。
- これによって「死亡診断書」を自宅で発行してもらえる可能性が大幅に高まり、警察介入を避けやすくなります。
- 延命措置・救急搬送の意思表示(ADL・ACP含む)
- 本人が「穏やかな最期」を望む場合は、事前に「救急車を呼ばない(蘇生措置不要)」という意思を医師や家族と共有しておきましょう。
- 〈人生会議〉や〈リビング・ウィル〉(生前意思表明書)を用意し、緊急時に救急隊などへ意思が示せると、無用な対応を避けられます。
- 危篤状態との線引き確認
- 「蘇生の可能性が全くない」死亡状態が明確であれば、救急車ではなく警察に通報(110番)するのが正しい対応です。
- ただし、判断に迷う場合は迷わず「救急車(119番)」へ連絡し、救急相談センター♯7119でアドバイスを得るのが安全です。
- 遺体への対応(現場保存)
- 自宅で亡くなった場合、警察や医師による検視が行われることがあるため、必ず遺体を動かさず、そのままにしておく必要があります。
📝 実践例(ステップ形式)
| 状況 | コンタクト先 | 方法 |
| ① かかりつけ医(訪問医)がいる | 医師/訪問看護師 | まず電話連絡。医師が死亡確認・診断書作成。 |
| ② 蘇生可能性あり(判断つかないとき) | 救急車(119)/♯7119 | 専門家の判断を仰ぐ。 |
| ③ 死亡が明白(冷たい、死斑あり) | 警察(110) | 現場保存した上で通報。検視・検案書発行。 |
『心に鬼を魂に炎を』やはり、このような感情を抱くのは「鬼」なのだろうか?
電子書籍としてBOOK☆WALKERで購入可能
🔑 要点まとめ
- かかりつけ医がいるかどうかで対応の流れは大きく変わります。
- 医師との連絡体制の事前設定や意思表明準備が、遺族負担を減らすために重要です。
- 現場保存や通報方法を遺族が共有しておくことで、警察介入や救急車待機のストレスを軽減できます。
鬼岩氏の『心に鬼を 魂に炎を』の趣旨にも通じる、自分と大切な人の最期を「穏やかに、尊厳をもって迎える」ための準備――家族で話し合い、在宅ケア体制を整え、意思を共有しておくこと。それが最も効果的で、遺族への過度な負担を避ける道筋です。