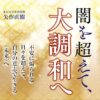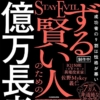消費税減税よりも定額給付を!マスメディアに騙されるな!消費税は消費額の大きい人の方が減税額も当然大きくなるのですから、高所得者の方がより大きな利益を得ることとなる!
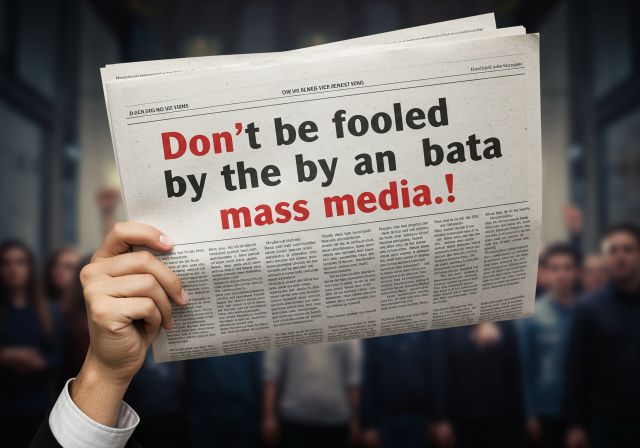
消費税を減税した場合、高所得・高消費世帯ほど絶対額で大きな恩恵を受ける一方、低所得世帯は相対的にその効果が小さくなることがシミュレーションで示されています。これに対し、一律の定額給付は受給額が全ての世帯で同額となるため、低所得世帯ほど可処分所得に占める給付の割合が大きく、再分配効果や貧困抑制の観点から優位性があります。本回答では、先行研究・政府試算をもとに両政策の分配影響を比較します。
消費税減税の分配効果
逆進性とその緩和策
消費税は、消費性向が高い低所得者ほど所得に占める負担率が高くなる「逆進性」をもつため、税率引き上げ時には低所得者対策が必須とされています。
減税による恩恵額の分布
- 財務省シミュレーションでは、世帯年収200万円未満の場合の年間負担軽減額は8,372円、1,500万円以上では17,762円と、年収区分によって2倍以上の差が生じます。
- 同試算によると、軽減税率導入による税収ロス総額4,598億円のうち、年収550万円未満の世帯が50.1%(約2,302億円)、同550万円以上が49.9%(約2,296億円)を占め、高所得世帯にもほぼ同程度の恩恵が分配されています。
- OECD加盟国平均と比べても、消費支出階層間の恩恵差は日本で約5,300円、OECD平均では約400ユーロと大きく、日本では高所得層への分配偏重が相対的に大きいと指摘されています。
定額給付の分配効果
給付制度の概要
2020年の特別定額給付金では、住民基本台帳に記載のある全ての国民に対し1人10万円を一律支給しました。
低所得世帯への影響
- 家計簿アプリデータを用いた分析では、等価所得の下位3分の1の世帯で給付額の約32%が消費に回され、低所得世帯の生活下支えに大きな効果があった可能性が示されています。
- 同じ分析では、中上位所得層では有意な消費増効果が見られず、給付金の経済的インパクトが低所得層に集中していたことが示唆されます。
- また、内閣府の家計調査推計では、給付金の消費押し上げ効果は家計簿データで22%、家計調査データで17%程度とされ、全体的にも一定の消費刺激効果が確認されています。
- 使途をみると、年収300万円未満層では「日常の買い物にまわした」割合が最も高く、低所得世帯の生活必需品支出へのダイレクトな支援となっています。
比較と政策的含意
- 絶対額 vs. 相対額:消費税減税は支出額に比例して恩恵額が増えるため、高所得層が絶対的に大きな利益を得るのに対し、一律給付は全員同額であり、低所得層ほど所得比でのメリットが大きい。
- 再分配効果:貧困抑制や所得再分配の観点では、定額給付がより強い効果を発揮しやすい。
- 経済刺激効果:一律給付はMPC(限界消費性向)の高い低所得層に効果的に資金が流れ、短期的な消費押し上げに貢献しやすい。一方、減税は高所得層に吸収されやすく、景気浮揚効果は限定的となる可能性があります。
- 政策目的による選択:持続的な財政運営や制度設計上の簡素さを重視するなら単一税率維持と減税が、分配・福祉重視なら定額給付が適切とされるでしょう。
以上を踏まえ、国民の幅広い所得層に公平・効果的に支援を行うためには、定額給付の併用や給付付き税額控除など多様な手法を組み合わせることが望ましいと言えます。