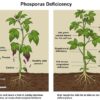「自由」と「自分勝手」を考え違いしている人が多いように見受けられる。自由とは義務と責任の上に成り立つもので、義務や責任を果たすことでしか自由を得られないものと考えられているのだが、なぜ「自分勝手」を自由だと思い込むのか
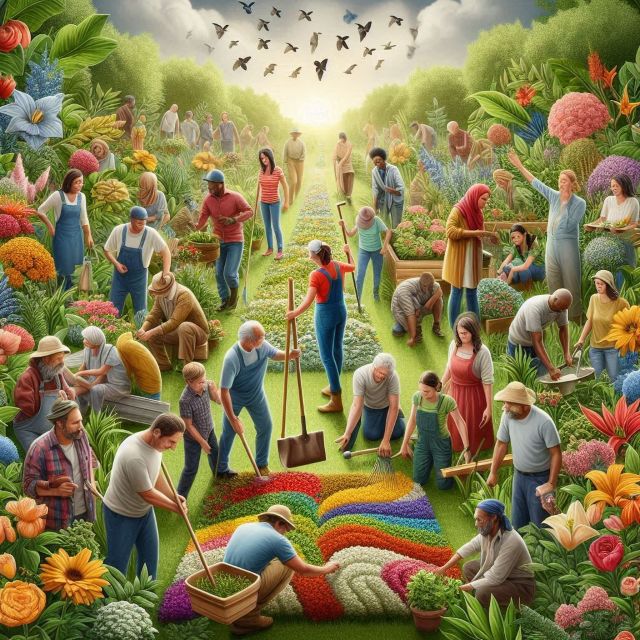
- 伝統的な価値観と近代化のギャップ
伝統的な日本社会では、家族や地域、職場といった集団の中での調和や協力、相互扶助が重んじられてきました。
その中では、個人の自由は自らの義務や責任を果たすことによって得られると理解され、自由=「他者への配慮や自己の責任の遂行」といった側面が強調されていました。しかし、戦後の高度経済成長やグローバル化、情報化の進展により、個人主義が強まるとともに「個人の権利」や「自己実現」が前面に出るようになりました。その結果、従来の「自由=義務や責任を伴う自律」から、単に「好きなように振る舞うこと」=「自分勝手」と解釈される傾向が生まれたと考えられます。
- 教育やメディアの影響
現代の教育やメディアは、個人の選択や自己表現を強調する傾向が強く、成功例や著名人の「自己主張」を賛美する場面が多く見られます。この影響で、自己中心的な行動が「自由」だと誤認されやすくなり、他者との共生や社会的責任といった側面が軽視されることに繋がっているのかもしれません。
- 社会的変容と価値観の多様化
グローバル化の影響で、かつては集団主義的だった日本社会にも多様な価値観が流入しました。結果、従来の「自由は責任の上に成り立つ」という考え方と、欧米的な「自分のやりたいようにする自由」との間に認識のギャップが生じ、後者の側面が目立つようになったと考えられます。
- 個人の成功志向の高まり
経済のグローバル化と競争の激化に伴い、個人が自らのキャリアや生活の成功に強く焦点を合わせるようになりました。その結果、個人の利益を最優先する「自己実現」が重視され、他者との連帯や社会的責任が二の次にされる場合もあります。このような風潮が「自分勝手」を自由と捉える認識に結びついていると考えられます。
結論
要するに、日本人の中で「自由」と「自分勝手」を混同する背景には、伝統的な集団主義に根ざす「自由=義務や責任の遂行」という概念が、近代化・グローバル化や教育・メディアの影響、そして個人の成功志向の高まりにより、次第に薄れていったことが挙げられます。現代社会では、個人の権利が強調されるあまり、自由を「好きなようにする権利」と捉えがちになり、結果として「他者への配慮や責任」を伴わない行動が「自由」として誤解されやすくなっているのです。