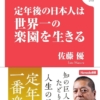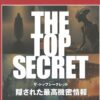参議院議員選挙で与党が過半数を取れなかったことにより、日本の政局不安から7月20日の投開票日以降10日程度はドル・円相場は円安傾向になるかと思いきや、実際には円高傾向にあります。その原因を考察

参議院選挙後のドル/円相場動向(7/20~30)の要因分析
日本の政局不安と市場の受け止め方
参議院選で与党が過半数割れとなり、選挙前には「不安定な政局=円安」予想が強かったものの、市場は選挙結果を「衝撃ではなく織り込み済み」と受け止めました。実際、米国市場では選挙翌日の7/21に円が対ドルで上昇(円高)し始めました。これは選挙前の「噂で売って事実で買う」動きの典型例で、選挙前に円安を見込んでいた売りポジションが一掃された結果とみられます。市場関係者も「結果は大方織り込み済み」「政治的不透明感がすぐに高まるわけではない」と述べており、短期的な円高基調となりました。
- 選挙前は与党敗北で財政・財源不安を懸念する円売り圧力が先行。
- 選挙結果は想定通りで衝撃的サプライズには至らず、「事実で買い戻し」の動きが円を押し上げた。
- 大手アナリストも「参院選は実質“ノーサプライズ”」と評価し、目立った円売り要因にならなかったと指摘している。
日本銀行の政策スタンスと市場予想の変化
日銀は最近まで金融緩和継続・利上げに慎重な姿勢を示しており、市場が次の利上げを意識するのは早くても秋以降と見られています。日銀自身も「米国の通商摩擦不透明感がなくならない限り慌てて利上げしない」(上田総裁)と繰り返してきました。7月開催の次回会合では金融政策据え置きが予想され、事前のエコノミスト調査でも7~9月における追加利上げは大勢的に「なし」見通しでした。しかし一方で、6月CPIが市場予想並みの伸び(前年同月比3.3%)となり物価上昇が持続する中で、年末にかけて日米金利差縮小→円安方向と見る見方も根強いです。
- 6月の全国コアCPIは前年同月比3.3%上昇で高止まりし、日銀の2%目標を大きく超過。これは物価圧力が依然強いことを示し、見通し改訂で追加利上げ期待を誘発。
- しかし日銀は米国の通商摩擦や景気への懸念から慎重姿勢を崩しておらず、7月会合では据え置きを固持する見込み。ブルームバーグ調査では年内に追加利上げする可能性は大きくなく、むしろ来年度に利上げ開始の可能性が高いとの見方が示されています。
- ただし貿易協定による関税問題の進展など、外部環境の好転は「日銀の利上げ再開」を意識させており、協定後には短期金利上昇圧力が強まりました。実際、選挙後に日米間で自動車関税15%合意が発表された7/23には、日本の国債利回りが急上昇し2年債も0.83%まで高騰しました。
- 以上から、市場では短期的な利上げ実施は消化されつつも、利上げ確率は秋以降に高まるとの見方が広がっています。
米国の金利・経済指標・FRB動向
米国では6月消費者物価が予想を上回りドル高圧力となりました。これを受けドル/円は7/16に一時149.19円まで上昇しました(年初来高値近辺)。しかしその後は米長期金利が低下し、ドルはやや軟化しました。FRBは7月末の会合で据え置きが大方予想されており、イエレン前議長の解任騒動報道後も市場は短期金利の急変を織り込みませんでした。こうした金利差拡大の期待縮小と、米経済指標に見られるピークアウト感が、ドルの下押し要因となっています。
- 米CPI・経済指標: 6月のCPI速報値は前年同月比+2.7%と上昇し、一時ドル/円急騰。ただし7月にかけては市場心理が慎重になり、ドル高圧力はやや低下しました。
- FRB動向: 7月末FRB会合では現状維持が確実視されており、早期利下げも大勢予想はされていません。トランプ大統領のパウエル解任示唆報道も市場混乱には至りませんでした。
- 通商政策: 米国側の対日交渉進展(自動車関税引き下げ合意)はドル売り要因となりましたが、その後伝えられた巨額投資計画報道でドル需要が再燃するなど方向感は交錯しました。
地政学リスクとリスク回避の円買い
地政学的リスクが円高要因になる場面でも、今回の期間はそれ以上に供給面の要因が作用しました。6月中旬の中東緊迫(イスラエル・イラン情勢)に伴う原油価格上昇が、日本の貿易収支を一段と悪化させており、通常の「有事の円買い」が相殺されました。シティのアナリストも「原油高は日本の国際収支を悪化させ、円を弱める」と指摘しており、結果的に円の安全資産的需要は限られています。市場全体ではむしろグローバルなリスク選好が改善し、株高・ドル高優勢の場面が目立ちました。
- 原油高: 中東情勢による原油急騰が輸入依存度の高い日本の収支を悪化させ、円安圧力として働いた。通常の地政学リスクに対する円高要因を相殺する構図です。
- 世界のリスク許容度: この期間中は米国や世界経済に大崩れはなく、株高・リスクオンの流れが継続しました。ニューヨーク市場ではリスク回避的な円買いは小幅にとどまりました。
- 金利環境: 低インフレ・低金利が続く日本と比べ、米長期金利の相対上昇が続いたことも円安圧力となりました。日米金利差が円高要因に転じる材料は特段出ませんでした。
その他の材料
- 対米投資拡大: 7/22の日米貿易協定では、日本側が米国への新規投資5,500億ドルを約束しました。大規模な資金流出期待が「円売り材料」として意識されており、協定発表直後の円高が一転、円安圧力に繋がるとの見方があります。
- 財政拡大観測: 石破首相の退陣報道は「新首相による減税・財政拡大策」を誘引するとされ、円売り要因視されました。国内金利上昇や利上げ期待が高まっている割には円安圧力が強かった背景には、こうした財政拡大観測があったとみられます。
- 構造的要因: 日本は2024年に大幅な貿易赤字・サービス収支赤字が続き、対米の直接投資や家計の海外投資も総額で数十兆円単位の円売りフローとなっています。これらの構造的な資本流出傾向は、一時的な投資資金流入があっても根強い円安要因として働きます。
- インフレ環境: 年初来で約7%超の物価上昇が日本で続いており、実質金利は大幅マイナスです。高インフレ下では通貨安になりやすいため、足元では円買いよりも物価懸念が重視されています。
まとめ
これらを総合すると、参院選後の円高は主に「事前織り込み済みの選挙結果」への反動や米国金利動向といった短期要因によるものと考えられます。しかし日銀の引き締め遅れや日米金利差、グローバルマクロ要因、構造的な資本流出が依然として円安を牽引しています。実際、選挙前から示唆されていた年末にかけての円安トレンド回帰予想も維持されており、今後は一時的な円高後に再び円安基調が優勢になる見通しです。ユーザーにとっては、単なる選挙ネタに留まらない幅広い要因が為替を動かしている点を理解することが重要です。