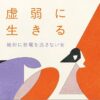「検査で見つかった無症状のガンを手術する必要はない」という医師がいるようですが、実際に放っておいても大丈夫なものなのでしょうか?大丈夫だとしたら自覚症状が出るまではそのままで大丈夫だということでしょうか?
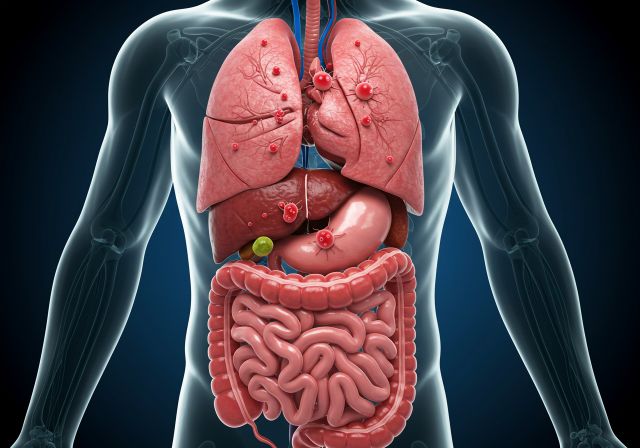
がんには、進行や転移のリスクが極めて低い「低リスクがん」と呼ばれるものがあり、こうした病変については手術などの積極的治療を直ちに行わずに、定期的な検査で経過を観察する“経過観察(active surveillance)”がガイドラインで認められています。代表例としては低リスク前立腺がん、甲状腺微小乳頭がん、小さな腎がんなどが挙げられ、患者さんの年齢・全身状態・余命予測、腫瘍の大きさや病理所見を総合して適応を判断します。自覚症状が出るのを待つだけではなく、画像検査や腫瘍マーカーなどで“成長や悪化の徴候”を厳密にモニターし、必要に応じて治療介入のタイミングを逃さないことが重要です。
経過観察(active surveillance)を採用する代表的ながん
前立腺がん
- 国際的なガイドライン(NCCNや欧州泌尿器科学会)では、低リスク前立腺がん(PSA低値、Gleasonスコア6以下、限局病変)に対し、手術や放射線治療を直ちに行わず経過観察を強く推奨しています。
- 日本泌尿器科学会のガイドラインでも、期待余命10年以上かつ無症状の低リスク例に対しては監視療法(active surveillance)を選択肢の一つと位置づけています。
- 患者向け資料によれば、経過観察中はPSA測定やMRI、必要に応じて生検を3~6ヶ月ごとに行い、病勢の進行が確認された時点で治療に移行します。
甲状腺微小乳頭がん
- 最大径1cm以下で、転移や局所浸潤のない“low-risk”微小乳頭がんについては、2015年の米国甲状腺学会(ATA)ガイドラインで経過観察が治療選択肢に加えられました。
- 日本でも同様に、甲状腺腫瘍診療ガイドライン2024において、無症状・低リスクの微小乳頭がんに対する積極的経過観察が推奨されています。
- 経過観察中は頸部超音波検査を6〜12ヶ月ごとに実施し、腫瘍径の増大やリンパ節転移の有無を厳重にチェックします。
小さな腎がん
- 腎がんでも腫瘍径が3cm程度以下で高齢者・合併症の多い患者に対しては、直ちに手術せず3〜6ヶ月間隔でCTやMRIを行い、成長率を観察する経過観察が選択肢となります。
- 患者の状態によっては、4cm以下のステージI腎がんで部分切除ではなく経過観察を検討するケースも報告されています。
経過観察の適応基準と管理方法
- 適応基準:全身状態良好で期待余命が一定以上(例:前立腺がんなら10年以上)、腫瘍が限局性・低悪性度、かつ患者が経過観察の意義とリスクを理解し同意していることが必須です。
- 管理方法:
- 専門医による詳細な説明と同意(インフォームドコンセント)を実施。
- 画像検査(超音波、MRI、CT)や腫瘍マーカー(PSAなど)の定期測定。
- 病変の増大、グレードの上昇、新たな転移兆候など“進行シグナル”を厳密に監視し、基準超過時には速やかに治療に切り替えます。
リスクと留意点
- 経過観察を選択すると、あくまで「進行リスクが低い」前提のもとで「積極的に治そうとしない」戦略であり、完全に放置するわけではありません。
- 画像やマーカーの変化を見逃すと、腫瘍が進行して手術適応外になったり、転移リスクが高まったりする可能性があります。
- 「がんもどき理論」として、一部医師は「無症状がんは放置しても命に別状なし」と主張しますが、科学的・臨床的エビデンスには乏しく、多くの専門学会は慎重なフォローアップを前提としています。
自覚症状が出るまで放置しても大丈夫?
- 自覚症状が出る段階は、しばしば病勢が進行し切迫したサインであるため、「症状が出るまで待つ」は危険です。
- 経過観察は「無症状でも定期検査で悪化をキャッチし、適切なタイミングで治療介入する」戦略であり、症状出現前に判断・対処します。
医師の意見が分かれる理由
- がんの過剰診断・過剰治療を避けたい立場から「無害ながんは放置すべき」と主張する医師がいる一方で、病勢進行の見逃しを恐れる医師は「早期手術が安心」と意見を異にしています。
- 患者の心理的負担や医療資源の最適活用、がん発見技術の高度化による偶発的診断増加など、背景事情が複合的に絡んで議論が続いています。
まとめと医療機関への相談のすすめ
- 無症状がんのすべてが「手術不要」とは限らず、がんの種類・ステージ・患者の状況に応じて、ガイドラインに則った経過観察か積極治療かを選択します。
- 自覚症状が出るまで放置するのではなく、「定期的検査で進行リスクを監視し、必要時に治療を行う」ことがポイントです。
- ご自身のがんが経過観察の適応かどうかは、専門医と十分にリスク・メリットを話し合ったうえで判断してください。