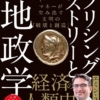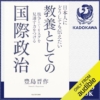【閉塞感の正体!】なぜ日本は変われないのか?「新卒一括・終身雇用・年功序列」の起源を明治時代から歴史社会学で徹底解明!雇用・教育・福祉を支配する“暗黙の慣習”の束を暴く必読の書!
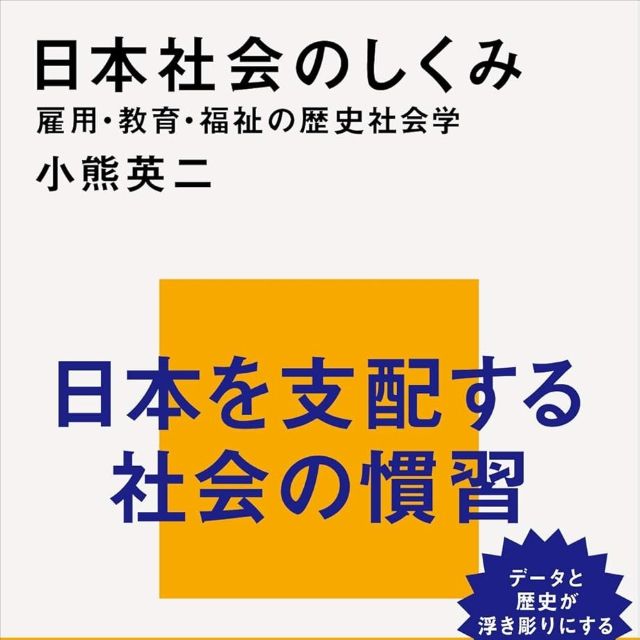
日本を呪縛する「暗黙のルール」— なぜ、私たちはこの「しくみ」から逃れられないのか?
「働き方改革」が叫ばれて久しいにもかかわらず、日本の労働環境はなかなか変わらず、長時間労働、低い生産性、そして正社員と非正規雇用との格差は広がる一方です。誰もがこの社会の「閉塞感」を感じていますが、その原因を「個人の努力不足」や「制度の不備」だけで片付けてしまうのは早計です。
社会学者・小熊英二氏の著書『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』は、この日本社会全体の生き方を規定している「暗黙のルール」—すなわち「慣習の束」の起源と変遷を、歴史を遡って解き明かす、極めて重要な一冊です。
【「当たり前」はいつ、どうやって生まれたか?】
私たちが「日本的」と認識している働き方の特徴—新卒一括採用、終身雇用、年功序列、定期的な人事異動—これらは、実は明治時代の官庁や軍隊にその起源を求めることができます。
本書は、これらの慣行が、特定の意図のもとで生み出されたのではなく、経営者、政府、そして労働者自身の力関係と妥協の産物として、複雑な歴史的経緯を経て、現代の「しくみ」として定着したことを明らかにします。
特に興味深いのは、欧米社会が「職務の平等」(同じ職務には同じ報酬)を目指したのに対し、日本の労働運動は「社員の平等」を追求した点です。これは、特定の職務に縛られず、経営側の裁量による異動や出向を受け入れる代わりに、学歴や勤続年数といった客観的な指標に基づいて、社員全員に平等な昇進・昇給の道を開く、という日本独自の「社内契約」を形成しました。
【3つの「生き方」が社会を支える】
著者は、現代の日本社会の生き方を、主に3つの類型に分けて分析します。
- 大企業型(約26%): 大企業の正社員とその家族。上記の「日本的雇用」の恩恵を最も受ける層。
- 地元型(約38%): 地方の自営業、農業、地場産業、地方公務員など。地域や家族の「ムラ」に支えられる層。
- 残余型(約36%): 上記のどちらにも属さない、非正規雇用や不安定な中小企業の労働者など。
日本の社会保障や教育システムは、主に「大企業」か「地域(ムラ)」のいずれかに足場があることを前提として設計されています。したがって、どちらにも属せない「残余型」の層が、不安定な生活を強いられ、社会保障の網からこぼれ落ちやすい構造になっていることを、データと歴史が明確に示しています。
【見直すべきは「慣習」そのもの】
本書の説得力は、この「しくみ」が、雇用だけでなく、教育、福祉、そして人々のアイデンティティやライフスタイルまでも規定していることを歴史的に証明している点にあります。この暗黙のルールを理解することなしに、どんな「改革」も表層的なものに終わってしまうでしょう。
約600ページという大部の新書ですが、その重厚な分析は、現代を生きる私たちが直面する閉塞感の根源を知り、「このしくみは変えられる」という視点を持つための、極めて貴重な羅針盤となります。あなたの働き方、あなたの家族の生き方が、なぜそうなっているのか。その真実を知るために、ぜひ手に取るべき一冊です。