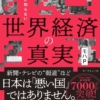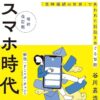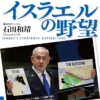【地政学/国際政治/歴史教養】 覇権はなぜ移り変わるのか?――帝国の興亡、二度の世界大戦、そして核抑止の時代へ。米中対立からウクライナ戦争まで、現代の力学を読み解く“世界のリアル”が一冊でわかる!
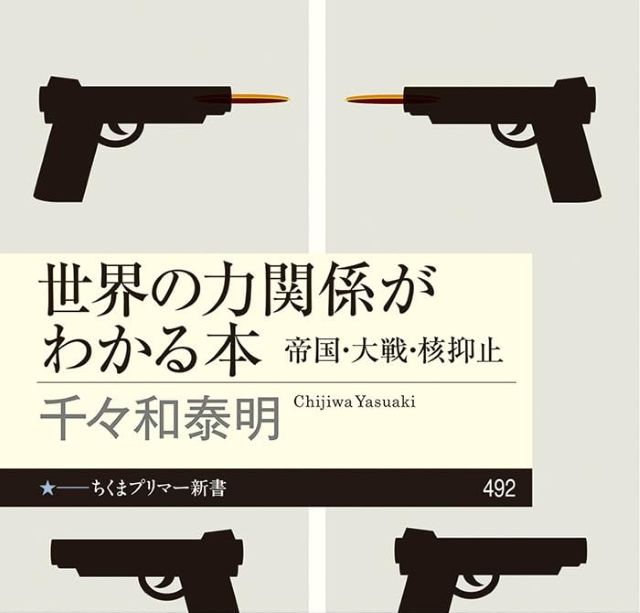
「なぜ世界は、常に“力”によって動いてきたのか?」
――その問いに真正面から挑むのが、『世界の力関係がわかる本 ――帝国・大戦・核抑止』だ。
古代ローマから現代のアメリカ、中国、そしてロシアに至るまで、国家の興亡を貫くのは“力”の論理。
本書は、歴史を単なる年表としてではなく、「力の構造」として読み解く。
戦争も平和も、外交も経済も、すべてはこの“力の配置”が決めてきたのだ。
著者はまず、帝国の時代を描く。
イギリス帝国の海上支配、オスマンやローマの覇権構造。
そこに共通するのは、「技術・経済・軍事・思想」が連動したときに初めて国家は“帝国”となるという原則だ。
しかし、どんな帝国も永遠ではない。
力の均衡が崩れるとき、歴史は新しい秩序を求めて動き出す。
続く章では、二度の世界大戦がいかにして勃発し、なぜ終結したのかを「力の移行」という視点から分析。
第一次大戦ではイギリスからアメリカへ、第二次大戦では欧州から超大国の時代へと、覇権の座は静かに移り変わっていく。
戦争は悲劇であると同時に、世界の構造を再編する“リセットボタン”でもあった。
そして、現代を決定づけたのが「核抑止」という力のバランスだ。
冷戦期の米ソ対立は、核兵器という究極の恐怖によって均衡を保った。
しかしその均衡は、恐るべき脆さの上に成り立っている。
本書は、抑止力の理論と現実のずれを明快に示し、21世紀の安全保障の本質に迫る。
著者の筆致は、難解な理論を排して平易である。
“国際政治は遠い世界の話ではない”というメッセージが全編に通底している。
ウクライナ侵攻、台湾問題、そして中東の緊張――。
これらの出来事は、教科書的な「正義」や「悪」では説明できない。
そこに働くのは、いつの時代も変わらぬ“力の論理”なのだ。
だが本書は、単なるリアリズムの主張に終わらない。
著者は同時に、「力の暴走をどう制御するか」という希望の糸口も提示する。
それが、外交・国際法・市民社会という“もう一つの力”である。
歴史を知ることは、未来を恐れることではなく、理解することなのだ。
読み終えたとき、あなたは世界のニュースがまったく違って見えるだろう。
「なぜ今、米中が対立しているのか」「なぜ小国の戦争が世界を揺るがすのか」――。
そのすべてに、一本の見えない糸が通っていることに気づくはずだ。
『世界の力関係がわかる本』は、教養としての歴史と、現代を生き抜くための知恵を同時に与えてくれる。
学生からビジネスパーソンまで、“世界の動きを自分の言葉で語れるようになる”ための入門書である。