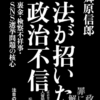日本の米農家が極めて小規模であることが生産性向上や所得確保の大きな障壁となっており、その背景には相続による細分化や高齢化・担い手不足、制度的・政策的硬直性があることがわかります。打開には、農地集積・法人化の促進、スマート農業技術の導入

現状:規模・生産性・所得の実態
- 平均作付面積は約1.5~1.8ha:日本の稲作農家は平均耕作面積が1.5ha程度と、米国(約98ha)の約100分の1、ドイツの約20分の1、英国の約38分の1という世界でも極めて小規模な経営が大多数を占めています。
- 農家戸数の急減:2000年の約174万戸から2020年には約70万戸へ半減し、全国の水稲収穫農家は約94万戸にまで減少しています。
- 高齢化の進行:基幹的農業従事者の平均年齢は66.8歳に達し、65歳以上が6割を占めています。
- 所得の低迷:
- 平均的な1.5ha規模の農家では、130俵(約7.8t)、粗収益約180万円を得ても、農薬・肥料・機械維持費などを差し引くと年間所得は数十万円にとどまります。
- 一方、20ha以上に拡大すると、農業所得は1,248万円超に跳ね上がるなど、規模拡大が所得に直結しています。
- 生産性の停滞:日本の農業は政策的保護が手厚く、2020~22年の生産者支援率(PSE)は収入の38%とOECD平均のほぼ2倍に達していますが、その一方で、生産性向上は遅れがちです。
原因分析
- 相続・細分化による小規模化
農地は相続時に均分相続の原則で細分化が進み、所有者単位での権利移動にも多くの制約があるため、耕作放棄地が増え、残る農地は極小面積のまま固定化しています。
- 高齢化・担い手不足
65歳以上の農業従事者が増加し、後継者不足が深刻化。耕作意欲をもつ若年層は、資金負担の大きさや不安定な所得から新規参入をためらい、地域全体で担い手確保が困難になっています。
- 制度的・政策的硬直性
- 農地法の制約や集落単位の農地バンク運営の煩雑さが、農地の効率的な貸借・集積を妨げています。
- 高い生産者支援率は短期的な安定化には寄与するものの、市場原理や規模拡大を促すインセンティブには逆行している面があります。
- 技術・資本投入のハードル
大規模化しないと機械化・ICT投資のコスト回収が見込めず、結果として人手依存の非効率経営が常態化。1ha程度では、高額機械の導入効果が見えにくく、省力化投資が進みません。
打開策(解決策)
- 農地集積・集約化の強化
- 農地中間管理機構の活用促進:集約型助成を拡充し、集積協力金などのインセンティブを強化。都道府県・市町村と一体となった地域計画を策定し、集積率80%以上を目指す。
- 農地バンク手続きの簡素化:手続きのデジタル化・ワンストップ化により、貸借マッチングを迅速化。
- 企業的・法人化の促進
- 農事組合法人・農業法人の支援:法人化による農地の集約/資本調達の円滑化、譲渡所得・相続税猶予の税制優遇を拡大し、規模拡大を後押し。
- スマート農業技術の導入支援
- スマート農業推進総合パッケージによる実証・普及、人材育成、補助金・税制優遇を一体的に提供し、IoT・AI・ロボット技術導入を加速させる。
- スマート農業技術活用促進法の認定制度で金融支援を拡充し、10ha以上の担い手がデータ駆動型農業にシフトしやすい環境を整備。
- 人材育成・新規参入支援
- 農業経営者育成学校・研修機会の拡充:自治体とJAが連携し、地域の営農技術から経営ノウハウまで学べる場を設置。
- 若手・女性・Uターン就農支援:就農費用補助、雇用就農資金による研修・生活支援を強化し、就農のハードルを低減。
- 法制度改革(相続・税制)
- 均分相続の見直し検討:相続協議期間の明確化や見なし分割制度の導入で、農地細分化を抑制。
- 相続税・贈与税の納税猶予拡大:農業承継を条件とした納税猶予の要件緩和で、農地の集約的承継を促進。
- 6次産業化・多角化支援
- 加工・観光・直販を組み合わせた6次産業化を補助し、農産物の付加価値を向上。地域ブランド化や直売所、デジタル販路(EC)支援を強化。
以上のように、単一の施策ではなく、農地・経営規模・技術・人材・法制度の各側面を連動させた総合的施策が、小規模な米農家の生産性向上と所得改善を実現する鍵となります。