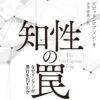日本における「外国人に対する生活保護」が必要な明確な理由はあるのでしょうか?そもそも日本での生活保護は憲法第25条の、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という条文を根拠としている

憲法文言とその解釈
- 憲法第25条の「国民」:
憲法第25条は「すべて国民は…」と規定しており、この「国民」という語は、国家の一員としての権利と義務を持つ主体を指します。つまり、国家がその構成員である「国民」に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障する義務を負うとの立場です。これを踏まえると、対象が外国人まで拡大されると、憲法の文言が本来意図した範囲を超えると解釈する見方が生じます。
国民性と社会契約の視点
- 政治的共同体としての国民:
生活保護制度は、国家とその国民との間の社会契約の一環として設計されています。国民は選挙権など政治的権利を通じて国家運営に参加し、互いに助け合うという共通のルールに基づいています。外国人の場合、たとえ在留期間が長く社会に溶け込んでいたとしても、政治的主体性や国家への帰属意識という点では国民とは異なる扱いになるとの主張があります。
拡大解釈の問題点
- 憲法文言の逸脱:
「すべて国民」という表現を、在留外国人にまで適用するのは、文言通りの解釈からは逸脱するという見解です。これを拡大解釈とする理由としては、国家の福祉提供の対象が、あくまで政治的共同体である国民に限定されるべきという考え方に基づいています。 - 制度的な一貫性:
生活保護を国民に限定することで、国家としての責任範囲と、税負担など相互の社会契約が明確になります。もし外国人にも無条件に拡大すれば、制度全体の公平性や持続可能性に疑問が生じる可能性があるという主張もあります。
まとめ
以上のように、憲法第25条の文言が「国民」に限定されていること、そして国家と国民との間の社会契約という観点から、外国人を含む全在留者に生活保護を拡大解釈するのは、法的・制度的な根拠を欠くとする論点が存在します。この立場からは、生活保護の対象は憲法上明確に定められた「国民」に限定されるべきであり、外国人にまで適用することは、憲法の原文の趣旨を逸脱する拡大解釈であると説明されるわけです。