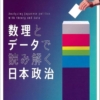トランプ大統領のイラン核施設攻撃によりドル相場が高騰しています。そもそもトランプ大統領は貿易赤字解消のためドル安にけん引していたと思われますが、なぜこのような望郷に出たと考えられますか?

トランプ大統領のイラン核施設攻撃というニュースを受けて、ドル相場が高騰したとのことですが、これは非常に複雑な事象が絡み合って発生する現象です。ご指摘の通り、トランプ政権は貿易赤字解消のためにドル安を志向する発言を繰り返していました。それにもかかわらず、今回の局面でドルが高騰した背景には、地政学リスクと「有事のドル買い」という特殊な市場心理が働いたと考えられます。
以下に、その理由を詳しく解説します。
- 地政学リスクと「有事のドル買い」
国際情勢が緊迫し、地政学的なリスクが高まると、世界の投資家はリスクを回避しようとします。その際、最も安全な資産とみなされる通貨や資産に資金が集中する傾向があります。この現象を「有事の○○買い」と呼びます。
- 米ドルの「基軸通貨」としての地位: 米ドルは、世界の貿易や金融取引で最も広く利用されている「基軸通貨」です。そのため、国際的な混乱が発生すると、多くの国や企業がドル建ての資産を保有していることや、ドルが流動性が高く、いつでも現金化しやすいという特性から、安全な避難先として選ばれやすくなります。
- 米国の経済規模と安定性への信頼: たとえ政治的な混乱があったとしても、米国の経済規模は依然として世界最大であり、その安定性に対する信頼は厚いものがあります。これもドルが「安全資産」として認識される大きな理由です。
- 金融市場の流動性: 米国の金融市場は世界で最も流動性が高く、大規模な資金の出し入れが容易です。有事の際には、資金を迅速に移動させたいというニーズが高まるため、流動性の高いドルが選ばれやすいのです。
イランへの核施設攻撃は、中東地域の緊張を一気に高め、世界経済の先行きに対する不透明感を増幅させました。このような状況下では、たとえ攻撃主体が米国であっても、世界の投資家は安全を求めてドルに資金を集中させる「有事のドル買い」の動きが強まります。
- トランプ大統領のドル安志向との矛盾について
ご指摘の通り、トランプ大統領は歴代の米大統領の中でも異例なほど、ドル高が米国の貿易赤字を拡大させていると主張し、FRB(連邦準備制度理事会)に利下げを求めるなど、意図的にドル安に誘導したい意向を強く示していました。これは、米国の輸出競争力を高め、国内製造業を活性化させ、最終的に貿易赤字を解消するという経済政策の目標と密接に関連しています。
しかし、今回のイラン攻撃によるドル高は、トランプ大統領の意図とは異なる結果として現れています。これは、以下の点が考えられます。
- 経済政策と安全保障政策の優先順位: 大統領にとって、自国の経済政策目標は重要ですが、それ以上に国家の安全保障は最優先されるべき課題です。イランの核開発は、米国の国家安全保障に対する直接的な脅威と認識されており、この脅威を取り除くための行動が経済的な影響を一時的に引き起こすことは許容範囲と判断された可能性があります。
- 短期的な市場の反応と長期的な政策目標の乖離: 地政学リスクに伴う「有事のドル買い」は、市場の瞬間的な反応であり、短期的な動きです。トランプ政権のドル安誘導という政策目標は、より長期的な経済構造の改善を目指すものであり、短期的な市場の反応によってその目標を放棄するものではありません。大統領は、今回の軍事行動がもたらす短期的なドル高を認識しつつも、それよりもイランの核開発問題への対処を優先したと考えられます。
- 国内支持層へのアピール: トランプ大統領は、強硬な姿勢で米国の国益を守ることを支持層にアピールする傾向があります。イランに対する強硬な姿勢は、その支持層の期待に応えるものであり、次期大統領選を意識した行動である可能性も否定できません。
結論
トランプ大統領が貿易赤字解消のためにドル安を志向していたにもかかわらず、イラン核施設攻撃によってドル相場が高騰したのは、地政学リスクの高まりによる「有事のドル買い」が、大統領の経済政策目標よりも短期的な市場の安全志向を優先させた結果であると考えられます。
大統領は、国家安全保障上の判断としてイランへの攻撃を決定し、その結果として発生する短期的な市場の反応(ドル高)は容認した、あるいは、それを上回る安全保障上の利益があると判断した、と推測できます。