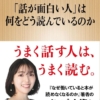ガソリン税の暫定税率廃止の約束はどうなったのか?消費税との二重課税問題はいつになったら解消されるのか?一般会計にして使い道をわかりにくくし、自分たちの自由にすることこそが財務省の狙いだったのか?

ガソリン税は1953~54年(昭和28~29年)に道路整備の特定財源として導入され、2008年度限りで廃止され、2009年度(平成21年度)以降は一般会計化されました。当初は暫定税率(1974年導入)を廃止する約束があったものの、その後も毎年延長され、現在も本則28.7円+暫定25.1円=計53.8円/ℓが維持され、さらにその総額に対して消費税が課される「二重課税」構造が続いています。一般会計化により、ガソリン税収(2024年度は約2兆0180億円、一般歳入の1.8%)は各省庁の予算に組み込まれ、社会保障、公共事業、防衛など多様な歳出に配分されるため、本来の道路整備への使途が見えにくくなっています。
- 道路特定財源制度の導入と一般会計化
1.1 制度創設と特定財源の役割
- 昭和28年に「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」で揮発油税が道路整備の特定財源とされ、自動車利用者が維持・整備費を負担する仕組みが始まりました。
- その後、自動車取得税や自動車重量税なども道路特定財源に組み入れられ、目的税として機能していました。
1.2 一般会計化の経緯
- 2008年2月の税制抜本改革で、道路特定財源制度の規定を廃止し、平成21年度(2009年度)から全額を一般財源化する法改正が閣議決定されました。
- これにより、2008年度限りで道路特定財源は廃止され、2009年4月以降の税収は国家予算の一般会計に組み込まれることとなりました。
- 暫定税率の導入とその継続
2.1 暫定税率の導入目的
- 1974年のオイルショック直後、道路整備の財源不足解消を目的に本則税率(当時)に上乗せされ「暫定税率」が導入されました。
2.2 廃止の約束と実態
- 一般財源化の際には暫定税率も廃止検討とされたものの、以降も毎年租税特別措置法で延長され、現在に至ります。
- 2025年度税制改正大綱には「暫定税率廃止」が明記されたものの、具体的な時期や代替財源が確定せず、2026年4月廃止が有力視される段階です。
2.3 現行税率と構成
- 現在、ガソリン税は本則28.7円/ℓに暫定25.1円/ℓを上乗せし、合わせて53.8円/ℓが課されており、さらに石油石炭税2.8円、消費税(ガソリン本体+諸税額の10%)が加わります。
- 二重課税の問題
- ガソリンの消費税は「本体価格+ガソリン税や石油税等の合計額」に対して10%が課されるため、ガソリン税にも消費税がかかる二重課税状態となっています。
- この仕組みは「Tax on Tax」として長年批判されており、消費税適用時に諸税額を控除すべきとの声があります。
- 一般会計化による使途の不透明化
4.1 ガソリン税収の一般会計組み込み
- 令和6年度一般会計歳入では、揮発油税を含む自動車関係諸税が合計約9兆円(租税総収入の7.7%)を占め、揮発油税単独でも約2兆0180億円(1.8%)が計上されています。
4.2 予算配分の実態
- 一般会計歳出では、公共事業関係費(道路整備を含む)が歳出総額の約7.5%、社会保障が55.7%を占めるなど、歳入と歳出の直接的な対応は示されず、道路整備に充てられる割合は予算全体の一部に埋没しています。
- 予算編成は年度ごとの歳出項目ごとに決定されるため、「ガソリン税収=道路整備費」という仕組みは廃止され、使途の透明性・追跡性は大幅に低下しました。
- 改善に向けた視点
- 再エアマーキング(用途指定):道路整備分を予算化前にガソリン税収から直接差し引く方式を導入し、再び受益者負担の原則を復活させる手法。
- 予算情報の可視化:政府が年度ごとにガソリン税収の使途内訳を公表し、道路整備への充当額を明示することで、納税者の理解と監視を可能にする。
- 暫定税率廃止と代替財源:暫定税率廃止に合わせ、燃費・走行距離連動課税など新たな仕組みを検討しつつ、累次延長された「暫定」を解消する。
以上のように、ガソリン税の一般会計化と暫定税率の延長により「道路整備のための税」という本来の目的は希薄化し、透明性も失われています。再度「特定財源」としての性格を明確化するか、または完全な一般財源として扱うならば暫定税率を廃止し、一層の開示強化が求められるでしょう。