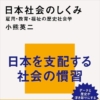現代の学校教育が多数の生徒を同時に教育することで成り立っている部分もありますが、現代社会においては個別主義が台頭していて、同じ空間にいてもそれぞれが全く別々のことをしていたりもします。この社会と学校の差異が不登校の大きな原因?

【物語:『透明な時間の中で』】
東京郊外の小さな町に、亮(りょう)という中学生がいた。亮は、朝早くから始まる一斉授業や決められたスケジュールに、次第に窮屈さを感じ始めていた。学校では、クラス全員が同じ教室に集まり、同じ教材を同じペースで学ぶ。しかし、亮の心は教室の中で静かにざわめいていた。彼は、SNSや動画、オンラインでの交流を通して、同じ空間にいながらもそれぞれが自由に、個別に生きる現代社会の姿を知っていた。
放課後、クラスメートたちは部活動や補習に参加する中、亮は一人自室で自分のペースで学び、好きな音楽を聴きながら考え事にふける。彼にとって、学校という「一斉進行」の場は、社会で求められる個別性や自由な発想とは大きく隔たりを感じさせる場所だった。
ある日、亮は自らの中にある違和感を抱えながら、ある教師と対話する機会を得る。その教師は、伝統的な教育方法に疑問を持ち、個々の才能や個性を伸ばすための新しい学びの形を模索していた。教師は亮に、「本当の学びとは、必ずしも皆で同じペースで進む必要はないんだ。君自身がどんな『自由』を大切にしているのか、考えてみよう」と語った。
その言葉は、亮の胸に小さな火をともした。彼は次第に、学校という枠組みが必ずしもすべての人に合うものではないのだと感じ始める。個々の生徒が、社会ではそれぞれが全く別の道を歩み、違った価値観を持って生きている現代日本において、画一的な学校教育が果たす役割と、そこに潜む「不自由」さを痛感したのだった。
次第に亮は、クラスに顔を出さず自宅学習へと移行する。不登校というレッテルを貼られることに恐れはあったが、彼は自分のペースで本当の「学び」や「成長」を追求する決意を固めた。家族や一部の教師は心配したが、やがて彼の姿勢は周囲にも理解され、地域では個々のペースを尊重する学びの場を作ろうという動きが生まれていった。
そして、亮がかつて感じた「学校」と「社会」のずれは、やがて一つの議論へと発展する。画一的な教育方法ではなく、生徒一人ひとりの才能や興味を尊重する個別学習の取り組みが、徐々に実験的に導入され、彼のような「不登校」と呼ばれる生徒たちにとっても、新たな学びの場が生まれていくのであった。
この物語は、現代日本における学校教育の画一性と、社会全体の個別主義の高まりとのズレが、どのように不登校の背景の一因となり得るかを、主人公の内面の葛藤や対話を通じて描いています。