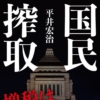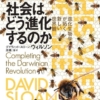【タブーに挑む】部落差別はなぜ現代に存在するのか?「属人的」から「属地的」へ変質した差別の実態を解明!「忌避意識」の構造と日常生活に潜む“見なされる差別”の深層に迫る!
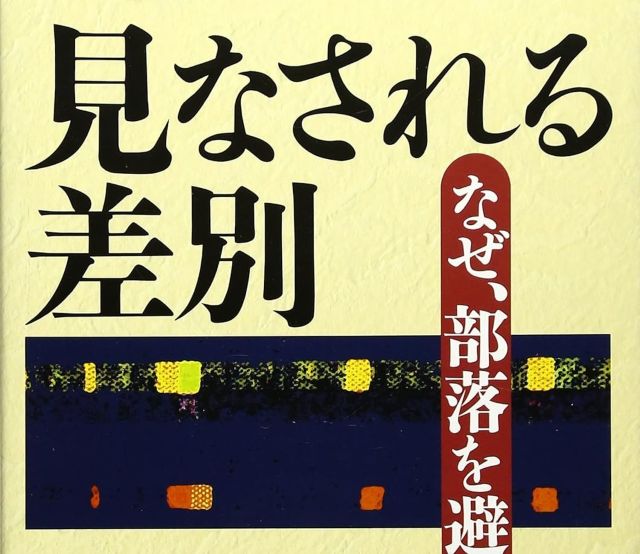
差別を再生産する「見えない壁」— 私たちは、なぜ部落問題を「避ける」のか?
現代社会において、「部落差別(同和問題)」は、依然として存在するにもかかわらず、公の場で語ることを避けられがちなテーマです。多くの人が「もう過去の問題だ」と認識するか、あるいは「触れてはいけないタブー」として沈黙を選びます。しかし、その「避けたい」という意識そのものが、差別を再生産するメカニズムとなっているとしたら、どうでしょうか?
奥田均氏の著書『見なされる差別 なぜ、部落を避けるのか』は、この現代に存在する部落差別の本質を、「見なされる差別」という新たな視点から深く掘り下げた、啓発的な一冊です。
本書の核心にあるのは、差別が、個人の出自に直接向けられる「属人的差別」から、ある特定の地域との「関連性」を基に見なされる「属地的差別」へと変質しているという分析です。
かつての差別は、特定の個人が「部落出身者」であると確定されることによって行われていました。しかし現代では、差別を忌避する人々が「自分が部落出身者と見なされたくない」、「自分の子どもが差別される地域に住んでいると見なされたくない」という、自己防衛的な「忌避意識」から、特定の地域を避け、その地域と関わることを拒否します。
この「忌避意識」こそが、現代の差別の構造を支える「見えない壁」です。
- 土地差別: 意識調査や日常の具体例から、特定の地域(同和地区)出身ではない人々が、その地域に住むことを嫌悪し、不動産取引などで不当に避ける「土地差別」の実態が明らかにされます。これは、特定の土地に住むだけで、自身が差別される対象と「見なされる」ことを恐れる論理に根差しています。
- 「誰が部落出身者か」という規定の拡大: 差別の主体が、自らの忌避意識を守るために、差別対象を拡大し、「部落出身者」の定義をあいまいにしていくプロセスが分析されます。この拡大こそが、不安と不信を生み、社会の分断を深めています。
- 対抗への模索: 著者は、この差別を再生産する「忌避意識」に対抗するためには、差別撤廃に向けた「社会的躾け」(教育)の形成と、部落の内外が協働し、地域を分断するこの壁を取り除くための模索が必要だと提唱します。
本書は、部落差別がなぜ人権問題として特別に扱われ続けるのか、そしてその構造がどのようにして私たちの日常生活や無意識に深く根ざしているのかを、非常に冷静なデータと論理で解き明かします。
「差別問題は難しい」「どうせ自分には関係ない」と蓋をしてきたすべての人に、本書は、目を背けてきた日本の社会問題の深層を直視させ、「差別とは、単なる偏見ではなく、社会構造が生み出す現象である」という重要な気づきを与えてくれるでしょう。差別のない社会を目指すための第一歩として、この「見なされる差別」の構造を理解することから始めてください。