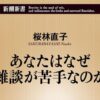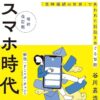今回のトランプ関税問題を含め軍事的・金融的には依然としてアメリカが主導権を握っている一方で、経済構造の変化や貿易協定の再編、製造業シェアの拡大などを通じて、中国が相対的影響力を高めつつあることが明らかに

- 経済的主導権
1.1 名目GDP比較
- 2023年のアメリカの名目GDPは約30.5兆ドルであり、世界最大の経済規模を維持しています。
- 同年の中国の名目GDPは約19.2兆ドルで、世界第2位に位置しています。
1.2 購買力平価(PPP)ベースのシェア
- 購買力平価ベースで見ると、中国は世界のGDPの19.29%を占め、主要国中最大のシェアです。
- アメリカは同じく14.84%で第2位にとどまっています。
1.3 成長率見通し(関税の影響)
- トランプ政権下の高関税政策を受け、IMFは2025年のアメリカ成長率を1.8%、中国を4.0%に下方修正しました。
1.4 貿易協定の再編
- アメリカは2017年に環太平洋パートナーシップ協定(TPP)から離脱し、自ら主導していた大規模多国間協定から退いたことで、地域内での経済的影響力を縮小させました。
- 一方、中国は15か国が参加するRCEP(地域的包括的経済連携)で貿易ルール作りの中心を担い、域内での経済重心をアジアにシフトさせています。
1.5 製造業シェア
- 中国は2023年に世界の製造業付加価値の29%を占め、単独で次点のアメリカ(約12%)を大きく引き離す存在となっています。
- 軍事的主導権
2.1 軍事支出
- SIPRIによると、アメリカの2023年軍事支出は9160億ドルで世界の37%を占め、依然として断トツの規模です。
- 中国は同年に2960億ドル(世界の12%)を支出し、2位の地位を堅持しています。
2.2 同盟関係
- アメリカは50か国以上と集団的安全保障や相互防衛条約を締結し、グローバルな同盟ネットワークを維持しています。
- 対して中国は正式な防衛同盟を持たず、経済的・外交的影響力の拡大を軸としています。
- 金融的主導権
3.1 準備通貨シェア
- IMFのCOFERデータでは、2024年第4四半期における米ドルの外貨準備シェアは57.8%と、依然として圧倒的な優位を保っています。
- 一方、中国人民元のシェアは2.18%にとどまり、大きな追い上げには至っていません。
3.2 国際機関での影響力
- IMFや世界銀行においてアメリカは最大の出資国および議決権を保持しており、仮に米国が支持を撤回すれば、これら機関の運営や世界金融システムに大きな動揺をもたらす一方で、中国の影響力が相対的に強まります。
- 技術・ソフトパワーとその他
4.1 技術競争
- トランプ関税問題では半導体や電気自動車などのハイテク分野で相互制裁・禁輸措置が強化され、米中双方の技術覇権争いが激化しました。
4.2 ソフトパワー
- 中国は一帯一路やCPTPP加盟申請など経済外交を通じた影響力拡大を図る一方、米国はクアッドや日米豪印協力など安全保障面での結束を強めています(詳細は前述の軍事同盟参照)。
総括:
現状では、軍事力・金融システム・同盟ネットワークを軸にアメリカが依然として主導権を握っています。一方で、経済構造の変化(製造業シェアの拡大、PPPベースでのGDP規模)や多国間貿易協定の再編(TPP離脱→RCEP台頭)を通じて、中国は相対的な影響力を高めつつあります。トランプ関税問題はアメリカの「予測不可能性」を浮き彫りにし、中国が地域ルール作りで優位に立つ機会を生みましたが、全体として米中二極化は続くものの、主導権の完全移譲には至っていません。