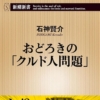教義の柔軟性から受け入れられた「仏教」一神教ゆえの排他性と、他宗教への弾圧が招いた「キリスト教弾圧」洗礼や信仰告白など儀礼は日本の多神教的儀礼習慣と相容れず、改宗者には神社参詣の放棄や祖先祭祀の中止が求められるとは

日本において仏教は、神道との神仏習合による多神教的寛容性と教義の柔軟性によって受容が進んだ。一方、キリスト教は一神教ゆえの排他性と、神々の共存を前提としない教義が日本の八百万の神信仰と相容れず、さらに外国勢力への帰属意識や政治的脅威とみなされたため、豊臣・徳川政権下で弾圧された。
仏教受容の背景
神仏習合と多神教的寛容
- 中世以降、日本では神道の神々(kami)と仏教の諸仏を相互に習合させる神仏習合が広く行われ、神も仏も共に崇敬する形で共生したため、仏教は「外来宗教」でありながら異質感なく根付いた。
- 仏教が来来した際、「仏は別人格ではなく、土着の神々の一種と解釈できる」という柔軟な受容態度が日本人に共有され、仏教の各宗派は神道祭祀や祖霊信仰と容易に結びついた。
仏教の教義的柔軟性
- 仏教は輪廻や因果律といった教義が多神教的世界観と競合せず、むしろ祖先供養や死後世界観を補完する役割を果たしたため、「生まれるときは神道、死ぬときは仏教」という慣習が定着した。
- また、神道における「もののあわれ」や自然崇拝の感性は、禅仏教や浄土教の思想とも親和性が高く、両者の教理的対立が起きにくかった。
キリスト教の受容困難性
一神教の排他性
- キリスト教は「唯一神のみを崇拝せよ」とする排他的信仰を持ち、神道の八百万の神々や先祖崇拝との両立が構造的に困難だった。
- さらに、洗礼や信仰告白など儀礼は日本の多神教的儀礼習慣と相容れず、改宗者には神社参詣の放棄や祖先祭祀の中止が求められ、社会的孤立を招いた。
宗教的・政治的脅威
- キリスト教は教皇庁と欧州列強の背後支援を想起させ、領国主権を脅かす“外来の勢力”とみなされた。
- 布教活動は宣教師による情報交換の拠点ともなりうるため、統治体制の監視下に置く必要性が強調された。
キリスト教弾圧の経緯と理由
豊臣政権下の弾圧(1587年)
- 豊臣秀吉は1587年、南蛮貿易の利益を維持しつつも、宣教師の布教活動を「政治的扇動」と見做し、伴天連追放令(バテレン追放令)を発布して宣教師を国外退去とした。
江戸時代の禁教令と鎖国(1614年~)
- 徳川家康・家光らはキリスト教を外交・交易権の交渉カードとしつつも、最終的に1614年に全国的な禁教令を出し、教会や宣教師の破壊・国外追放、信徒の摘発・処刑を制度化した。
- 鎖国政策下ではオランダ商館のみが限定的に交易を許され、キリスト教の持ち込み経路は断絶された。
島原の乱と徹底的な弾圧(1637–38年)
- 島原の乱では、地元領主の重税に対する一揆にキリシタンが加担したとされ、約3万7千人が犠牲となる惨事となったことから、徳川政権は「キリスト教=内乱の温床」と断定し、以後300年以上の隠れキリシタン時代に突入した。
- この乱の影響で、当局は信徒への踏み絵や宗門改帳など厳格な検挙・拷問体制を整備し、キリスト教徒は地下に潜るしかなかった。
結論
仏教は神道と多層的に融和し、日本文化に柔軟に適応したのに対し、キリスト教は一神教の排他性と欧州列強との結び付きゆえに外来の脅威とみなされた。その結果、豊臣期の追放令から徳川期の禁教・鎖国・徹底的弾圧へと繋がり、日本人の宗教的多神教的寛容性との齟齬が最終的に「キリスト教弾圧」の大きな要因となったと推察される。