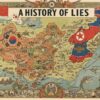日本人同士では言葉に出すまでもなく相手のことを理解する、あるいは理解してくれるものだというのが常識。これに対し「多文化共生」などという考え方では「日本人側が変わるべき」という論調になりやすい。日本人が日本国の中で外国人に同調?!
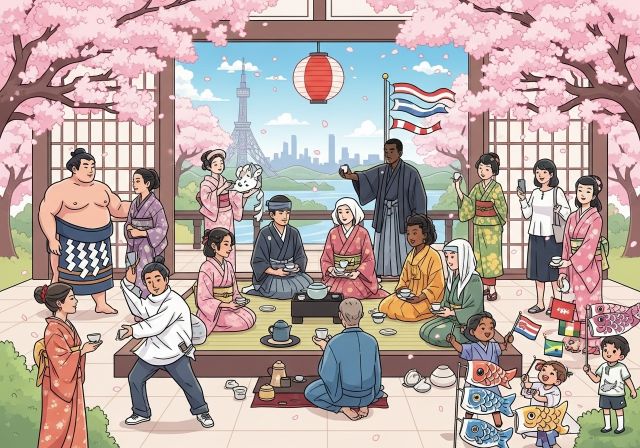
日本の文化における「以心伝心」という考え方と、他国における「言葉による対話」の重要性は、たしかに異なる文化的な価値観であり、この違いが多文化共生における課題としてしばしば議論されます。
日本文化の「以心伝心」と多文化共生
「言うに及ばず」や「以心伝心」といった考え方は、ハイコンテクスト文化と呼ばれる特徴の一つです。これは、言葉にされない文脈や空気を読み取ることで円滑なコミュニケーションをはかる文化を指します。
一方で、多くの欧米諸国などではローコンテクスト文化が主流で、意図や感情を言葉で明確に伝えることが重視されます。ディベートや議論は、お互いの意見をはっきりと述べ、その違いを理解し、より良い結論を導き出すための重要なプロセスと考えられています。
多文化共生における「日本人側が変わるべき」という議論
「多文化共生」という考え方では、「日本人側が変わるべき」という論調になる背景には、以下のような理由が考えられます。
- 異なる文化の理解と尊重: 異なる文化的背景を持つ人々が共存するためには、どちらか一方が一方的に従うのではなく、お互いが歩み寄り、相手の文化を理解し、尊重することが不可欠とされます。日本に住む外国人が日本の文化を学ぶのと同様に、日本人もまた、外国人文化を理解し、彼らが暮らしやすい社会を築く努力が求められます。
- 社会のダイバーシティ: 世界のグローバル化が進む中、日本も外国人労働者や居住者の増加により、社会の多様性が増しています。多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、社会全体の活力向上につながると考えられています。そのためには、日本独自の文化や習慣だけでなく、多様な文化的背景を持つ人々に配慮した柔軟な社会システムやコミュニケーションのあり方が必要となります。
どこまで「同調」する必要があるのか
ご指摘の通り、「日本という国家の中では日本としての文化に従うべき」という考え方にも一理あります。
多文化共生とは、必ずしも「日本人が外国人の文化に同調すること」を意味するものではありません。むしろ、異なる文化を持つ人々が、お互いのアイデンティティや価値観を尊重しつつ、共通のルールやマナーを共有して共に暮らす社会を目指すものです。
例えば、電車の中でのマナーや公共の場での振る舞いなど、社会生活を送る上での基本的なルールは、そこに住む全ての人々が守る必要があります。しかし、個人の思想や宗教、家庭内の習慣など、他者に迷惑をかけない範囲においては、その多様性が尊重されるべきだという考え方が一般的です。
この問題は、「日本の文化を守る」ことと「多様性を受け入れる」ことのバランスをどうとるかという、非常に複雑で奥深い課題です。どちらか一方の考え方に固執するのではなく、両者の視点を理解し、対話を通じてより良い社会のあり方を模索していくことが重要だといえるでしょう。