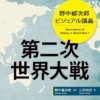多動力、好奇心、クリティカルシンキング…「話が面白い人」は何を読み、どう話すのか?ビジネスパーソン必読の書、ここにあり。
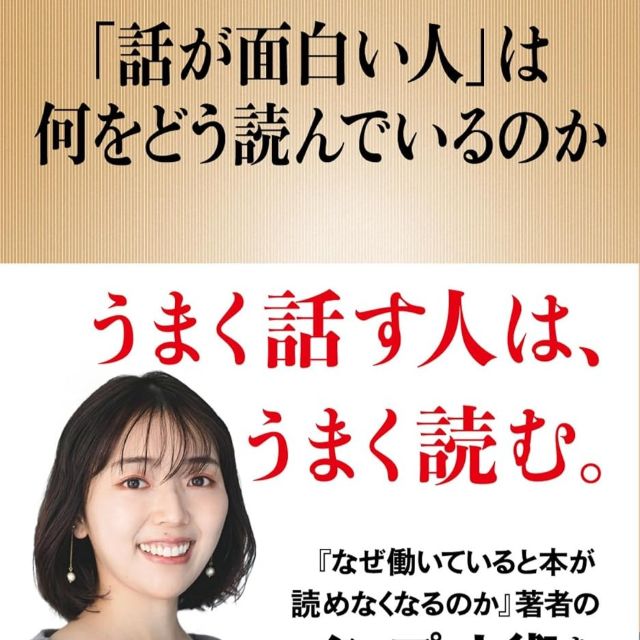
「あの人と話していると、なぜか引き込まれる」「話が面白い人って、いったい何を考えているんだろう?」
そう思ったことはありませんか?本書『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(新潮新書)は、その疑問に明確な答えを与えてくれます。著者は、元博報堂のコピーライターであり、多方面で活躍するベストセラー作家、古賀史健氏。彼の言葉は、常に私たちを深く考えさせ、新たな視点を与えてくれます。
この本が説く「話が面白い人」になるための鍵は、意外なほどシンプルです。それは、「読む力」と「話す力」を鍛えること。しかし、単に多くの本を読むことではありません。本書が教えてくれるのは、いかにして「深く読むか」、そしてその読んだ内容を「魅力的に話すか」という、実践的なスキルです。
なぜ、読書が「面白い話」につながるのか
本書の核心は、「読むことは、他者と対話することである」という哲学です。私たちは本を読むとき、著者という他者の思考や経験に触れます。それは、まさに彼らと対話しているのと同じこと。著者の考えを吸収し、自分の頭で咀嚼し、問いを立てる。このプロセスこそが、あなたの思考を深め、独自の視点を生み出す土壌となるのです。
「何を読んだらいいかわからない」「積ん読が増えるばかり」という悩みも、本書は軽やかに解決してくれます。古賀氏は、ジャンルを問わず、好奇心の赴くままに読むことの重要性を説きます。ビジネス書、小説、マンガ、雑誌、新聞…。一見バラバラに見える情報が、あなたの頭の中で思わぬ化学反応を起こし、新たなアイデアや視点につながるのです。
「ただ読む」から「アウトプットする」ための実践的ノウハウ
しかし、どれだけ読書しても、それを「面白い話」に変えられなければ意味がありません。本書は、そのための具体的な方法を惜しみなく提示しています。
たとえば、著者は「読書ノート」のつけ方を提案します。単に内容をまとめるのではなく、「なぜこの本に惹かれたのか」「著者の主張に違和感はないか」「自分ならどう考えるか」といった問いを書き留めることで、読んだ内容が血肉となっていきます。これは、まさに「自分自身との対話」であり、話の「切り口」を見つける訓練にもなります。
また、「話すことは、相手と場を共有することである」という視点も非常に示唆に富んでいます。面白い話とは、ただ知識をひけらかすことではありません。相手の興味を引き出し、共感を呼び、共に笑い、共に考える。本書は、そのための「聞き方」「質問の仕方」「ストーリーテリングの技術」といった、実践的なコミュニケーション術についても深く掘り下げています。
変化の激しい時代を生き抜くための「知的筋力」
私たちは今、膨大な情報に囲まれて生きています。SNSやニュースサイトから次々と流れてくる情報に振り回され、表面的な知識ばかりが増えていく感覚に陥ることはないでしょうか。
『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』は、そのような現代社会を生き抜くための「知的筋力」を養うための指南書です。単なる小手先のテクニックではなく、思考の根幹を鍛える方法を教えてくれます。
読書を通じて自分自身と向き合い、他者と対話する。そして、その過程で得られた独自の視点や言葉で、人々を魅了する。この本を読み終えたとき、きっとあなたは、これまでとは違う読書の楽しみ方、そして、人と話すことの喜びを見つけることができるでしょう。
もしあなたが「もっと話がうまくなりたい」「自分の言葉で人を動かしたい」と願うなら、ぜひ本書を手に取ってみてください。あなたの日常に、そしてビジネスに、大きな変化をもたらしてくれる一冊になるはずです。